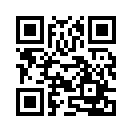2011種子取祭3
2011年12月04日
12月でも夕方になると蚊がブンブン飛んでいる石垣島からこんばんは。
今日は集中して注文のはんこをほりほりほりー。
何とか一つ仕上がりそうです。でも今日はもう一つ彫る予定。
がんばろ〜〜
そして種子取祭3です
種子取祭を最後まで観た事がある人は知ってるかもしれませんが、
後半はちょっとオモシロい。

こちら「サングルロ」という踊り。
全国竹富島文化協会さんから引用↓(以下赤文字同)
喜舎場永均さんは、『八重山古謡』の中で、ザングルロという題名でこの歌を載せており、
もっとも難解な歌であると述べている。
踊りそのものも、他の人重山舞踊とは大きく異なつており、踊り手の衣装も特異である。
赤く染めた芭蕉の糸で顔を覆い、黒頭巾を頭に被って踊る。
この踊りの最後は、四人の踊り手が転がりながら幕内へと入ってゆくが、その様子を、
俵を転がしていると解釈し、サングルロの「グルロ」は、転がる様を表現した言葉であるといわれている。
また、玉城憲文さんは、『竹富島仲筋村の芸能』の中でサングルロとは、
サングクダーラ(三石俵)が訛った言葉であると述べており、その踊りの由来を次のように述べている。
人頭税時代、百姓たちは、何とか年貢を逃れようと、子供が成長しても、
まだ大人になっていないように見せるためいろいろと工夫をした。
それに対して士族たちは、下着のない時代だったので、その子供たちに、
このサングルロを踊らせ、転がるのを見て、大人かどうか見極めたという。
これはかなり興味深い。遠い過去に往来していた南方系の文化と
八重山の文化が混在して新しいカタチになっているように感じる。
まさに芸能チャンプルー文化だ。
これにはみほちゃん出演♪
そしてこちらは大人気の「畑屋の願い」(猿狂言)
さる使い役のお父さんの本当の息子さんがお猿を演じてます。

「畑屋の願い」は、主とアヤーの夫婦が畑小屋で種子取の願いをしたり、
猿引きに出会って、猿の芸能を観るという筋である。
お猿の演技が最高です
名演技にお菓子やおひねりがバンバン飛んできます。
そして最後は泣かない子も泣く「鬼捕り」(鬼狂言)



この芸能は、西表の古見から竹富島に伝来したといわれているが、もともとは沖縄本島の芸能で、
登場人物は首里方言で語り、舞台も沖縄本島の本部山である。
福仲親雲上ふくなかぺーちんという棒術使いの武士は、
本部山に住む人喰い鬼を年け捕るようにとの命令を受ける。
福仲親雲上は、剣の達人である本村里主と、空手を得意とする佐久間里主とともに、
本部山の鬼退治に出かける。
一方、両親に捨てられた兄弟は、叔父さんに会うために、本部山の山中を歩いていたが、
兄は鬼にさらわれる。本部山に到着した3人の武士は、
それぞれの得意の技を披露して気持ちを落ち着けた後、鬼を探索して夫婦の鬼を捕え、兄を救出する。
兄からお礼を言われた福仲親雲上は、
「本村里主と佐久間里主には鬼を飼育させ、我はこの2人の子を育てよう」と言って、退場する。
子役の女の子は長い長いセリフを使い慣れない方言で、時々つかえながらも最後まで頑張って演じていました。
舞台セットが大掛かりで、ランタンで火を灯し、怪しい雰囲気が最高に盛り上がります。
そんな中、登場する迫力ある鬼に子供達はぎゃー!!と涙目。
あれだね、なまはげみたいなもんだね。
この芸を子供に観せたらしばらくは「言う事きかないと鬼がさらっていくよっ!」って言っても効き目あるかも。
まだまだ紹介しきれないものも沢山ありますが、私の2011種子取際の奉納芸能リポートはこれにて終了です
竹富島のみなさん、素晴らしい芸能をありがとうございました
明日は舞台裏をリポートした様子をUP します
さっ、これからまた制作でーす
 ← 一日一回ポチッとね♪
← 一日一回ポチッとね♪
今日は集中して注文のはんこをほりほりほりー。
何とか一つ仕上がりそうです。でも今日はもう一つ彫る予定。
がんばろ〜〜
そして種子取祭3です

種子取祭を最後まで観た事がある人は知ってるかもしれませんが、
後半はちょっとオモシロい。

こちら「サングルロ」という踊り。
全国竹富島文化協会さんから引用↓(以下赤文字同)
喜舎場永均さんは、『八重山古謡』の中で、ザングルロという題名でこの歌を載せており、
もっとも難解な歌であると述べている。
踊りそのものも、他の人重山舞踊とは大きく異なつており、踊り手の衣装も特異である。
赤く染めた芭蕉の糸で顔を覆い、黒頭巾を頭に被って踊る。
この踊りの最後は、四人の踊り手が転がりながら幕内へと入ってゆくが、その様子を、
俵を転がしていると解釈し、サングルロの「グルロ」は、転がる様を表現した言葉であるといわれている。
また、玉城憲文さんは、『竹富島仲筋村の芸能』の中でサングルロとは、
サングクダーラ(三石俵)が訛った言葉であると述べており、その踊りの由来を次のように述べている。
人頭税時代、百姓たちは、何とか年貢を逃れようと、子供が成長しても、
まだ大人になっていないように見せるためいろいろと工夫をした。
それに対して士族たちは、下着のない時代だったので、その子供たちに、
このサングルロを踊らせ、転がるのを見て、大人かどうか見極めたという。
これはかなり興味深い。遠い過去に往来していた南方系の文化と
八重山の文化が混在して新しいカタチになっているように感じる。
まさに芸能チャンプルー文化だ。
これにはみほちゃん出演♪
そしてこちらは大人気の「畑屋の願い」(猿狂言)
さる使い役のお父さんの本当の息子さんがお猿を演じてます。

「畑屋の願い」は、主とアヤーの夫婦が畑小屋で種子取の願いをしたり、
猿引きに出会って、猿の芸能を観るという筋である。
お猿の演技が最高です

名演技にお菓子やおひねりがバンバン飛んできます。
そして最後は泣かない子も泣く「鬼捕り」(鬼狂言)



この芸能は、西表の古見から竹富島に伝来したといわれているが、もともとは沖縄本島の芸能で、
登場人物は首里方言で語り、舞台も沖縄本島の本部山である。
福仲親雲上ふくなかぺーちんという棒術使いの武士は、
本部山に住む人喰い鬼を年け捕るようにとの命令を受ける。
福仲親雲上は、剣の達人である本村里主と、空手を得意とする佐久間里主とともに、
本部山の鬼退治に出かける。
一方、両親に捨てられた兄弟は、叔父さんに会うために、本部山の山中を歩いていたが、
兄は鬼にさらわれる。本部山に到着した3人の武士は、
それぞれの得意の技を披露して気持ちを落ち着けた後、鬼を探索して夫婦の鬼を捕え、兄を救出する。
兄からお礼を言われた福仲親雲上は、
「本村里主と佐久間里主には鬼を飼育させ、我はこの2人の子を育てよう」と言って、退場する。
子役の女の子は長い長いセリフを使い慣れない方言で、時々つかえながらも最後まで頑張って演じていました。
舞台セットが大掛かりで、ランタンで火を灯し、怪しい雰囲気が最高に盛り上がります。
そんな中、登場する迫力ある鬼に子供達はぎゃー!!と涙目。
あれだね、なまはげみたいなもんだね。
この芸を子供に観せたらしばらくは「言う事きかないと鬼がさらっていくよっ!」って言っても効き目あるかも。
まだまだ紹介しきれないものも沢山ありますが、私の2011種子取際の奉納芸能リポートはこれにて終了です

竹富島のみなさん、素晴らしい芸能をありがとうございました

明日は舞台裏をリポートした様子をUP します

さっ、これからまた制作でーす

 ← 一日一回ポチッとね♪
← 一日一回ポチッとね♪Posted by 楽種工房 kiyo at 20:19│Comments(0)
│竹富島